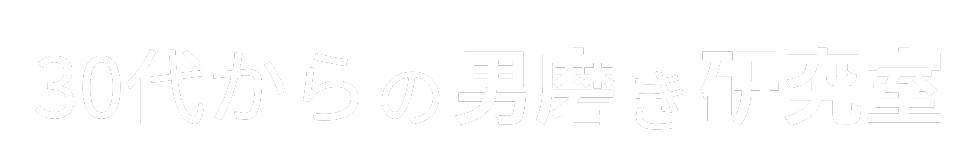「その疲れ、ただの夏バテじゃないかもしれない」──
年々厳しさを増す猛暑。“気合と根性”ではもう太刀打ちできない時代です。
30代を過ぎると、体は知らず知らずのうちに水分保持力や体温調節機能が低下していきます。
「ちゃんと水を飲んでいたのに」「日差しは避けたはずなのに」──
そんな油断から、突然の体調不良に見舞われるケースも少なくありません。
熱中症は、ただ暑いから起きるわけではありません。
水分・塩分・ミネラルの不足、睡眠やアルコールの影響、筋肉量の差まで。
実は、日頃のコンディションこそがリスクを左右するカギになります。
この夏を健やかに乗り切るために必要なのは、正しい知識と、戦える身体。
“倒れない体”は、一朝一夕ではつくれません。
今から備えておきましょう──猛暑に負けないコンディション。
なぜ熱中症になるのか?知っておきたい仕組みと原因
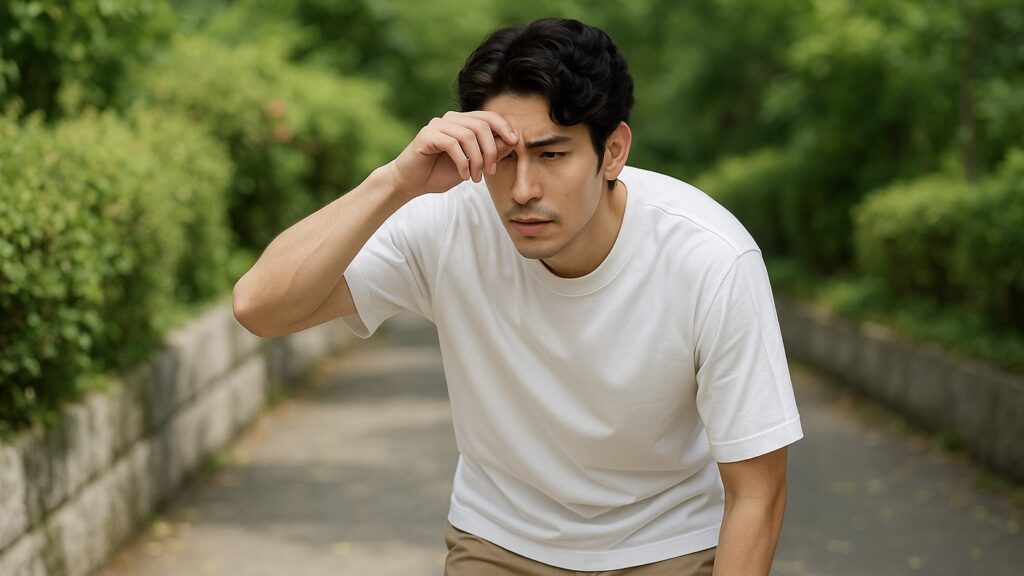
「なんだか体がだるい」「ふと立ちくらみがする」──
それ、ただの疲れではなく、熱中症のサインかもしれません。
熱中症は、体内の水分や塩分が不足し、体温調節が破綻することで起こる障害です。
汗で熱を逃がせるはずの体が、高温多湿の環境では機能しづらくなり、体内に熱がこもってしまうのです。
さらに、ナトリウムなどの塩分が失われることで、血流や神経の働きが乱れ、頭痛・吐き気・めまい、さらには意識障害を引き起こすケースもあります。
厚生労働省も、熱中症を「予防できる災害」として警鐘を鳴らしています。
まずは、そのメカニズムを正しく理解することが“守りの第一歩”です。
“水を飲むだけ”では足りない。正しい水分補給のルール

「水さえ飲めば大丈夫」と思っていませんか?
その考え方が、逆に脱水を招くこともあります。
発汗によって体から失われるのは、水分だけではありません。
ナトリウムやカリウムなどの“電解質”も同時に排出されます。
その状態で水だけを大量に摂ると、体液の濃度が薄まり、脱水が進行してしまう──
これが「自発的脱水」と呼ばれる現象です。
たとえば、汗をなめるとしょっぱいと感じたことはありませんか?
あの塩からさは、体に必要な塩分が失われている証拠です。
だからこそ、水分だけでなく“塩分補給”も必須なのです。
厚労省の『熱中症予防ガイドライン』でも、0.1〜0.2%の食塩を含んだ水分補給が推奨されています。
経口補水液やスポーツドリンクの活用が現実的です。
また、水分は一気に摂るより「こまめに」摂るのが基本。
30分に一度、コップ半分程度を目安に、「喉が渇く前」に補給しましょう。
たとえ屋内でも、気づかぬうちに汗をかいているもの。
「まだ大丈夫」ではなく「先に飲む」が夏の鉄則です。
そして、いざというときに備えて、経口補水液は自宅に常備しておくのが安心。
もし熱中症になったら。すぐに取るべき応急処置と判断の目安
「ちょっとフラついただけ」と油断していると、命に関わる場合もあります。
熱中症の重症度に応じた“正しい応急対応”を知っておくことが、命を守るカギです。
【軽度(I度)】
顔のほてり、ふらつき、足がつるなど。
→ すぐに日陰や涼しい場所へ。衣服を緩め、首・脇・足の付け根を冷却しながら、水分と塩分を補給。
【中等度(II度)】
頭痛、吐き気、強い倦怠感、集中力の低下など。
→ 冷却と補水を行いつつ、医療機関へ速やかに連絡・受診。
【重度(III度)】
意識障害、けいれん、異常行動、歩行困難など。
→ ただちに119番通報し、医師の指示を仰ぎながら、冷却・補水を継続。
判断が遅れるほど、リスクは高まります。
「おかしいかも」と思った瞬間が、対応のタイミングです。
“迷ったら休ませる・冷やす・飲ませる”を基本に、無理は絶対に禁物です。
筋肉は“水のタンク”鍛えることが最高の熱中症対策になる理由
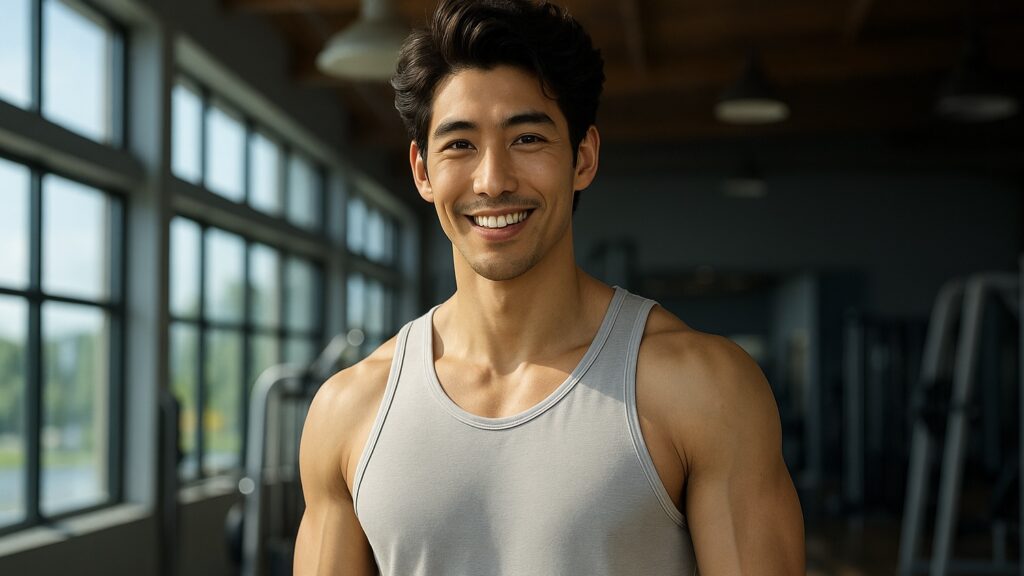
「鍛えた体は、倒れにくい」──
その理由は、筋肉が“水のタンク”だからです。
筋肉1kgあたりには約700gの水分が含まれており、体内水分の40〜50%は筋肉内に存在しています(『健康のための水分摂取ガイドライン|厚生労働省・2019』より)
つまり、筋肉量が多い人ほど体内に水分を蓄える力が高く、熱中症に強い体だといえるのです。
加えて、定期的な運動によって「暑熱順化」も進みます。
これは、体が暑さに適応し、汗のかき方や体温調節機能が効率よく働くようになる反応。
『日本生気象学会ガイドライン(2022)』では、1日30分の軽い有酸素運動を5〜14日続けることで暑熱順化が得られると示されています。
筋肉をつける、体を動かすことは、単なる美容や健康維持にとどまりません。
「倒れない身体」をつくる、いわば“防御力”の獲得でもあるのです。
見落とされがちな“睡眠”と“アルコール”の落とし穴
熱中症対策は、前日の夜から始まっています。
睡眠不足は、自律神経のバランスを崩し、体温調節や発汗機能に悪影響を与えます。
『日本生理人類学会誌』では、睡眠の質の低下が体温上昇とパフォーマンス低下につながると報告されています。
さらに、アルコールには強い利尿作用があり、飲酒後は水分が体外へ排出されやすくなります。
しっかり飲んだつもりでも、翌朝には“乾いた体”になっていることも珍しくありません。
「昨日の疲れが抜けない」「少しの移動でもふらつく」
それは、すでに体が危険信号を出しているサインかもしれません。
“倒れない体”をつくるには、水分や塩分だけでなく、睡眠・飲酒を含めた日常習慣の見直しが必要です。
翌日の暑さに備えるのは、今日の夜から。
すでに夏は、始まっています。